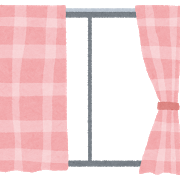七夕の風にひるがえるカーテン
ー①ー
山城窓
西面真人の楽しみ
「どうもカーテンになったらしいんだ」
「カーテン?」
「そう、カーテン」
そういって牧田は少しうつむく。その口は俺に何かを届けようと必死だが、その目は自信なさげで俺から逸れていく…そんな感じだ。
「唐崎っているだろ?」牧田が改めて告げる。「唐崎武雄。同じクラスにさ」
「いるね」
「その唐崎がさ、なったみたいなんだ。カーテンに」
「唐崎がカーテンになった?」
「そう」といって牧田はやはり目を伏せる。
その仕種に苛立ちながら、俺はいう。
「それを言うために、君はわざわざ俺の家にまで来たのか? 日曜日の昼間に?」
「ふざけているわけじゃないんだ」彼は弁解するように続ける。「もちろんまだちゃんと確かめたわけじゃないけど…でも確かめようがないし…」
彼は目を泳がせながら語る。事情はさっぱりわからないが彼は困っているようだ。俺は自分の部屋のカーテンに目を向ける。そのカーテンを指差して、俺は牧田に確認する。
「カーテンっていうのはあれだよな。その窓のところに吊り下がっている布のことだよな?」
「そう…。そのカーテンだよ。あ、でもこの部屋のカーテンじゃないんだ」
「じゃ、どこの部屋のカーテンになったんだ?」と仕方なく俺は尋ねる。
「三島江ゆかりは知ってるかな?」
「三島江ゆかり?」
「三組の…中学は東中だった。割と人気のある…」
「聞いたことはあるな。見たこともあるかもしれないけど…顔と名前は一致してない」
「見た目は色白でちょっと品のある感じの…」
「いいよ、説明は。それで、その三島江ゆかりがどうしたんだ?」
「その三島江ゆかりの部屋のカーテンになったらしいんだ」
「唐崎武雄が?」
「そう」
「三島江ゆかりの部屋のカーテンになった?」
「そう」
ここのところ蒸し暑い日が続いているが……正気を失うほどではあるまい。そんなことを思いながら、俺は椅子を軽く回して、突っ立っている牧田を促す。
「とりあえず、そこらへんに適当に座ってくれ」
「ああ、うん」と牧田は座り場所を探すようにキョロキョロと視線を散らしてから、ストンと落下するようにその場に座り込んだ。それを見届けてから、俺は尋ねた。
「今のところ君の話がどういう種類の話なのかもよくわからない。君の話し方でいいから、少し整理して話してくれ」
「ああ、うん」と臆病そうに彼は相槌を打つ。小柄な男というのは、こんな感じになるものなのかな、と思いながら、俺は勉強机に肩肘をつき彼の話を待つ。
「この間さ…もう三週間ぐらい前かな」と牧田は切り出す。「僕は唐崎の家に行ったんだ。アルバムを持って」
「アルバムって?」
「中学のときのアルバムを見せてくれってあいつが言うからさ。つまり僕は三島江ゆかりと同じ中学だったから」
「つまり唐崎は三島江ゆかりのことが好きだってことかな?」
「そうだよ、そう!」
「それを先に言うべきだったね。話がわかりにくい」
「それで、まあ唐崎の家でさ、三島江の話をいろいろとしてたんだよ。一年のとき、唐崎も三島江も別々のクラスで整美委員だったらしくて。で、その委員会でプリントを回すときに一回だけ言葉を交わしたそうなんだけど、唐崎はそのときの三島江の微笑みにヤラれたらしいんだ。何でも他の女子にはない清純さが感じられたそうだ」
「そのくだりを俺は聞かないといけないのか?」
「あの…まあ、それでさ、そんな話をしているときに…唐崎の肩にテントウ虫が止まったんだ。で、これは後から聞いたんだけどさ、『体にテントウ虫が止まると願いが叶う』っていわれてるらしいね?」
「聞いたことはあるけど…どっかの国の迷信だろ?」
「しかもその日の朝には彼は片目の白猫を見たらしいんだ。これは知ってるかな? 朝片目の白猫を見ると願いが叶うともいわれているんだ」
「知っているけど、それがなんだってんだよ?」
「しかも彼はその日『パンダのランデブー』っていうチョコスナックのお菓子を食べていて幻とも言われている『刀を携えたパンダ』が出てきたらしいんだ。それを食べると願いが叶うっていわれて…」
「だからそれがどうしたってんだ?」と俺は思わず彼の言葉を遮る。
「それで…」牧田はおもむろに言い直す。「その日から唐崎の姿が消えたんだ」
「消えた?」
「そう。学校にも来てないだろ? それで唐崎の母さんに相談されてたんだ。僕は唐崎の家にも何度か行ってたから唐崎と仲が良いと思われててさ。で、一度唐崎がいなくなった部屋を見せてもらったんだ。いなくなったそのままの状態でね。そしたら布団が敷いてあってそこに薄い毛布も掛けられてたんだけど…その毛布の下に唐崎の寝巻きが上下綺麗に揃えてあったんだ。まるで寝てる間に唐崎の体だけがそこから消されてしまったみたいに」
牧田は不安そうな表情で語る。俺にも少し話は見えてきたが……少しだけだ。この男が本気なのかどうかもまだわからない。俺が訝っていると、牧田は自分の鞄の中を探りながらいう。
「問題はこれなんだ」
彼はそこからノートを取り出す。そしてページをパラパラと繰る。「これだ」といって彼は手を止める。彼はそのページを指し示しながらノートを俺に渡す。
「唐崎のノートだよ。彼は詩を書いてたみたいなんだ。で、それが彼の書いた最後の詩みたいだ」
見ると確かにそこには、何かの詩が書かれている。随分と乱雑な字だが読めなくはない。タイトルは「カーテンでもいい」。
オレはただ君を見てるだけ 遠い遠いところで
抱きしめたい 口づけたい そばに寄り添いたい
でも嫌われるのが怖いから やっぱりキョリはつめられない
いっそオレは君の部屋のカーテンになりたい
いつもいつでも君をそばで見つめてられるから
言葉は交わせなくても
朝に開かれ、夜に閉じられ、そんなふうにアイサツできるから
君の笑顔も泣き顔も寝顔も見ていたい
美しい君のその顔の移り変わりは オレには素敵なストーリー
そのストーリーを追いかけていたいから やっぱりオレはカーテンになりたい
ジャマな光をさえぎったり 部屋の温もりを保ったり 少しは役に立つから
ずっとそばにいるから ずっと見つめてるから
見たくない君の姿を目にするときまで
「どう思う?」と牧田が俺の反応をうかがう。
「柄でもないことしてるものだね」と俺は正直な気持ちを零す。
「いや、そういうことじゃなくて……どう思う?」
「君が俺に何を訴えているのかはわかったよ」と俺はできるだけ冷静に応じる。「つまり唐崎は好きな人の部屋のカーテンになりたいという詩を書いてた。それで神様か何かがその願いを叶えてしまって、唐崎は三島江ゆかりの部屋のカーテンになった。君はそう言っているんだろ?」
「まあ…そういうことだね」牧田は少し恥ずかしそうに反応する。自分ではその可能性を信じてこんでいるのに、他人に改めて言葉にされるとやはり恥ずかしいようだ。
「これもあったんだ」と牧田は突然に言い足す。揺らぐ自分を咄嗟に支えようとでもするような慌てた感じで。彼は鞄から出したピンクの紐のようなものを俺に渡す。
「これがどうしたんだ?」渡された俺はそういってそれをぼんやり見つめる。
「なんていうのか知らないけど…カーテンを束ねて留めておくやつみたいだ」
「カーテンタッセルだね」と俺は教えてみる。
「カーテンタッセル?」これはカーテンタッセルっていうのか…って顔で牧田はぼんやりと俺を見つめる。が、やがて気を取り直すようにして続ける。「まあ、とにかくこのカーテンタッセルが唐崎の部屋に残されてたんだ。唐崎のパジャマの袖口辺りを巻くような感じで。唐崎の部屋のものかと思ったけど、それ唐崎の部屋のカーテンとは色が合わない。唐崎のお母さんに聞いてみたら『知らないわ、うちのじゃないみたいよ』ってことだった。だからもしかしたら…」
「三島江の部屋のものだって言いたいのか?」
「そりゃもちろんわからないけどさ…」牧田は躊躇いながらも何かを思い出すように続ける。「でも三島江も言ってたんだ。ちゃんと話したわけじゃないんだけど…僕と三島江の家はすぐ近所でさ。時々登校中に会うんだ。それでなんとなく気になったからさりげなく聞いてみた。『最近カーテンに何か変わったことはなかったかな?』って」
「その質問は絶対に『さりげなく』はなかったろうね」
「まあ、でもどう訊けばいいかわからないからさ。そう訊いてみたんだ。そしたらさ、言ってたんだ。夜中にカーテンの辺りが激しく光ったことがあるって。雷かと思って見てみたけど空は全然晴れてたって。で、後で確かめるとそれは唐崎が消えたのと同じ日だったんだ」
「それで」俺は気になって尋ねた。「カーテンタッセルは? 三島江ゆかりの部屋のカーテンタッセルはどうだったんだ?」
「………訊けなかった」
「どうして?」
「だって……最初の質問で気味悪がられてたし。そもそもそんなに親しくしてるわけでもないし……っていうか小学校の低学年までは一緒に遊んだりもしたけど…なんかいつのまにか向こうだけ大人になってるみたいで、でも僕は身長もいまいち伸びなくて、向こうはなんか人気もあって、それなりに華もあるけど、僕は冴えない情けない男で……」
「何の話をしてるんだよ?」と俺は思わず話を止める。
「いや、だから、全然僕と彼女はステージが違うというか、対等な関係じゃないんだ」
「見ればわかるよ」五頭身でいがぐり頭の牧田は、未だに中学生の雰囲気を拭い去れていない。
「とにかくそんなんだから……それ以上つっこんだことは訊けなかった。なんか変な目で見られていたし…」
「まあ、そうだろうな」
「そんなこんなで、」と牧田は改めて告げる。「唐崎はカーテンになってるらしいんだ」
俺は改めて牧田を観察する。…冗談を言っている顔には見えない。不安そうで、怯えているようでもあって、そして財布を失くした人のようにそわそわと落ち着きがない。こんな調子でカーテンに何かあったかとか言い出したら、そりゃ大体の人は気味悪がるだろうな、と俺は合点する。
「で、どうしようっていうんだよ?」と俺は尋ねる。
「どうしようって……決まってるじゃないか? 助けないと」
「助ける?」
「だってこのことを知っているのは僕だけだし…いや、一応話してはみたんだ。警察に。でもやっぱりなんか僕が『かわいそうな子』みたいに見られて、ちゃんと取り合ってくれないし。唐崎の親にも話してみようとしたけど…なんかやっぱりいえないし…」
「わからないな」と俺はいう。
「何が?」
「いや、ほとんどわからないんだけど…まあでも、今わからないと思ったのはそれをどうして俺に話したのかってことだね。俺は君とそんなに仲良くなった覚えはない。唐崎ともクラスメイトというだけで、殆ど話したこともない。そんな俺にどうしてそれを話すんだ?」
「だって…」牧田は伏せていた目をまっすぐ俺に向けていう。「西面君は変わり者だろ? なんでも父親が芸人だか劇団員だかやってるとか聞くし…」
「芸人であり劇団員だよ。本当の父親がね」
「本当の父親?」
「複雑なんだ」そういって俺はまた問い直す。「それより父親がどうであれ、そんなことで俺が変人ってことにはならんだろ?」
「でも西面君自身も…奇行を見せたり、よくわからないことを言ったりしてるじゃないか? ソフトボールの試合でヒットを打ってさ、一塁を駆け抜けて外野まで行ったと思ったら、そのままグランドを出てその日は結局帰ってこなかったりさ。『走馬灯職人っていうのは死に際に今まで作った走馬灯が走馬灯のように思い出されるんだろう』とかいったり。この間も…先生に変な言いがかりをつけてたじゃないか? 『恐竜が六五〇〇万年前に滅んだとどうして言い切れるんだ?』なんていっちゃってさ」
「言っておくけど」俺は堂々と主張する。「あれは俺が言っていることが正論だよ。だって恐竜がその時期に滅んだっていうことを誰もその目で確かめてないんだよ。その時期以降に痕跡が見つかっていないっていうだけのことで、その時期に滅んだって言っているほうが暴論だ。その可能性が高いっていうなら意味がわかるが、断言するのはおかしいってことだよ。そもそも恐竜がこの地球上に生きていたって証拠すらないんだぜ」
「何を言っているんだよ?」牧田は不思議そうに問い掛ける。「生きていた証拠はあるだろ? 化石がいっぱい見つかっているじゃないか?」
「だからそれは地球上に生きていた証拠にはならないんだよ。もしかしたら恐竜っていうのは宇宙人のペットだったかもしれない。それで死んだらその死体を地球に埋葬していたのかもしれない。だから六五〇〇万年前を期に化石やらの痕跡が見つかっていないっていうのは単にその時期に宇宙人の間で恐竜ブームが終わったというだけのことかもしれない」
「非常識な話だね」と牧田は少し嘲笑うような目を見せていう。
「常識に捉われて、その他の可能性から目を逸らすような愚かな生き方はしていないからね、俺は」
「だから君なんだよ」牧田は今度は嬉しそうな目を見せていう。「実際に君は今も僕の話をちゃんと聞いてくれた。他の人ならそうはいかなかった。君も不思議そうな目は見せたけどさ、それ以上に興味深そうだった。だから…頼むよ」
俺は牧田から目を切って考える。確かに…牧田の言うとおり、俺はいわゆる変人だ。そして…不思議なことは好きだし、それを探っていくことは俺の楽しみの一つでもある。それに……ここのところ気持ちも晴れない。一つ確かなのは…動いてみないと何もわからないってことだな。
「いいだろう」と俺は呟くようにいう。
「やっぱり」と牧田は顔を綻ばせて喜ぶ。「君は信じてくれたんだね?」
「信じたわけじゃないよ。ただ…神様っていうのは結構無茶苦茶するものらしいからね。確かめたい気持ちはある。『唐崎がカーテンになったかどうか』っていうことはね。それに…」
「それに?」
「もしかしたらこれは俺にとっても何かのきっかけかもしれない」
「どういうこと?」
「俺も今朝見たんだよ。片目の白猫をね」
すぐに俺たちは自転車に乗って唐崎の家へ行く。どこか古めかしい住居が建ち並ぶ集落にそれはある。インターフォンを押すと、たっぷりとした間を置いて、唐崎の母親が出てくる。昼寝の途中に起こされたような、締まりのない表情で。容姿はどことなく唐崎に似て…おおざっぱなつくりになっている。そして…髪には「おばちゃん」であることをアピールするようなパーマが掛けられている。
「何かわかったの?」と彼女は牧田に迫る。
「いえ…とくにわかったことはないんですけど…」迫力に押されているのか、彼は言い訳をするようにしゃべる。「まだ武雄君は戻ってないんですか?」
「そうよ。あれっきりよ。本当に困ったものね。もう三週間でしょ? ただの家出だと思ってたんだけどねえ。ほら言ったでしょ? 前にもこういうことがあったんだけど、それは本当にただの家出で。その時はお祖母ちゃんのとこに隠れてたのよ。お祖母ちゃんも孫には甘いからねえ、『いつまでだってここにいていいんだよ』とか言ってたらしくて、いやいや、『いつまでだっていていいわけないだろう?』って話なんだけどね。その時はだって中学生だったよ、義務教育だっつうの。ま、だから今回もまたそんなところかと思ってたんだけど…どこにもいないみたいなのよねえ。警察にも届けてあるんだけど、本気で探してくれているのかしら? 体だけは私に似て丈夫だから、野垂れ死んでるってことはないと思うけど…それより留年になっちゃうわ。それが心配なのよ」
「三週間の欠席ならまだ留年になることはありませんよ…」と何故か牧田は恐る恐る告げる。
「でも学校から連絡あったのよ」とおばちゃんは続ける。「この間期末テストだったんでしょ? それをまるごと休んじゃったから、明日から追試を受けなきゃいけないらしいんだけど…ねえ? 当の本人がいないじゃないのよ。私が受けるわけにもいかないしねえ」
おばちゃんは冗談とも本気ともつかぬ表情でそうぼやく。
「大丈夫ですよ」と牧田はおばちゃんを慰めようとするかのようにいう。
「何が大丈夫なのよ?」とおばちゃんは凄む。
「あの…今日は彼を連れてきましたから…」と牧田は俺を紹介する。
「どうも」と俺はおばちゃんに会釈する。
「あんたは役に立つのかい?」とおばちゃんは失礼な態度で応じる。「牧田君のほうは何の役にも立たなかったよ。あんたは大丈夫なの?」
「なるほど」と俺は思わず思ったことをそのまま漏らす。「唐崎武雄ががさつなのは親譲りだったみたいですね」
「何?」おばちゃんは今度は俺に凄む。「あんた随分生意気みたいだね?」
「俺も親の教育が悪かったんです」
「あんた喧嘩売りに来たのかい?」
「彼は推理力がすごくあるんです」と牧田が慌てて俺をフォローする。「だから今日は来てもらったんです」
「なんだ、その設定は?」と俺はつい牧田に尋ねる。
「いいじゃないか、それで」牧田が小声で俺を制す。
「まあ、そうだねえ」とおばちゃんが独り言のように話す。「あんたともめても仕方ないんだよ。若いうちはどうしたってみんな生意気なものだしね。でもあんた生意気な態度を取るんなら、それだけのことしてくれなきゃ駄目だよ。できるのかい?」
「試してみないとわかりませんよ。だからここに来たんです。とりあえず部屋を見せてもらえますか?」
「いいけどね。だったらあんた今日中だよ」
「今日中?」
「今日中にあの子を見つけだしておくれよ」
「わかりました」
「そんなこと約束していいの?」と心配そうに牧田が俺に訊く。
「いいよ、別に。俺もこんなことに何日も掛けたくないからね。それに今日だめなら…俺はこの人と会う機会はないだろうし」俺は牧田にそう囁いてから、改めておばちゃんに問う。
「じゃ、お邪魔していいですか?」
「いいわよ、もう。面倒くさいから。好きにしなさいよ」本当に面倒くさそうにそういって、おばちゃんは俺たちを部屋へ通してくれた。
「クラスメイトというだけで部屋へ通すなんてさ、本当にがさつだよな」と唐崎の部屋で俺は牧田に呟く。おばちゃんは居間のほうに既に戻っているが、
「聞こえるよ」と牧田がシーと人差し指を口元で立てながらいう。「君もしかして…唐崎のことは嫌いなのか?」
「好きも嫌いもないな。殆ど話したこともないし」
「どうして話さない?」
「合うか合わないかでいえば、どう考えても合わないからね。もちろん自分と全然違うタイプの人ともそれなりに上手くやっていくことはできるだろう。でも全然違うタイプの人とは誤解やすれちがいが生じやすい。その結果、抱えきれないほどの苦しみ、癒えることのない傷を負うこともある。だから慎重になっている。そんなところだ」
「なんか、よくわからないな」
「いずれわかるよ、嫌でもね。そういう種類のトラブルやら傷やらは誰にもちゃんと用意されているみたいだから」
牧田のぼんやりとした顔を横目に、俺は部屋を探る。唐崎が消えたときの布団やら寝巻きやらはもうさすがに片付けられている。他は彼の勉強机があり、テレビがあり、箪笥があり…まあ普通の部屋だ。そして俺はカーテンに目をやる。どこにでもありそうな安物っぽいライトグリーンのカーテン。牧田から預かっていた淡いピンクのカーテンタッセルを手に取って見比べる。確かにこのタッセルはこの部屋のものではなさそうだ。そして気付く。結局確認は取れたが…新しい発見は何もない。
「そうだ」と俺はつい両手を合わせて声に出す。「ここに来ても仕方がないんだ」
「ここに来ても仕方がないって?」
「三島江ゆかりの部屋へ行かないといけないんだ」
「三島江の?」
「だってそうだろ? その部屋のカーテンになってるかもしれないわけだろ? そこに何かの痕跡があるかもしれない。それかタッセルで巻いてみたり、あるいはそのカーテンを揺さぶったり叩いたり…何なら火でも付けてみれば何か変化は生じるかもしれない」
「君は結構無茶苦茶なことを言うね?」
「仕方ないだろう。無茶苦茶な状況かもしれないんだから」
「それに…いきなり押しかけて三島江が部屋へ上げてくれると思うか?」
「どうにかなるさ。方法っていうのはね、目を凝らしていれば見つかるものなんだよ」
「唐崎の部屋へ上がるのとはわけが違うよ?」
「いいから、案内してくれよ。三島江ゆかりの家へ」