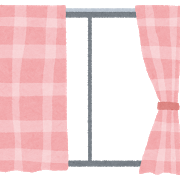七夕の風にひるがえるカーテン
ー③ー
山城窓
部屋を掃除して待っていると西面君がちょうど十九時に来た。ドキドキしながらも覚悟を決めて私は彼を二階の自分の部屋へ案内した。彼は部屋をキョロキョロと見回して…カーテンで目を止める。そのカーテンに歩み寄りながら、何かを思索しているような表情で両開きかあ」と呟く。そうか、彼はさっきの嘘の辻褄を合わせようとしてるのね。
「カーテンタッセルは?」と不意に彼が訊く。
「カーテンタッセルって?」
「カーテンを束ねる紐だよ。片方はそっちにあるけどさ」と西面君は窓の脇に掛かっている紐を示す。
「ああ、あれね」
「もう一つは? もう一つあるはずだろ?」
「もう一つ?」……そうね、もう一つあったはずよね。でも…「わかんない。いつのまにかなくなってたみたい」
「なくなった?」
「そうみたいね。私あれあんまり使ってなかったから…わかんないけど…」
「いつから? いつから見かけてない?」何故か彼は重大な事件の捜査でもしているように真剣な目で問い掛ける。
「覚えてないわ…そんなの。でも、結構最近かしら」
「お茶が飲みたい」と彼は唐突に訴える。「催促しているわけじゃないけどね」
そう催促された私は一階へ降りる。やっぱりあの人も緊張してるんだわ。なんだか上手く喋れないみたい。可愛いもんね。
紅茶を入れて戻ってきた私は「どうぞ」と丁寧にお盆に乗っけたグラスを渡す。彼は「ありがとう」と礼を言いながら、またカーテンに目を凝らす。つられて私もその視線の先を追う。あれ? カーテンが開けてある。っていうかカーテンがカーテンタッセルに束ねられて留めてある。
「それ…」とカーテンを示して私が声に出す。
彼は親指で背後のタッセルの辺りを示して尋ねる。
「これかな? この部屋のカーテンタッセルってさ?」
「そうよ、それよ!」
「落ちてあったから付けてみた。でも連絡は来ないな」
「ああそうなんだ。ありがとう。見つけてくれて」連絡は来ない? 何の話? それにしても、
「それどこに落ちてたの?」と私は訊いてみる。
「ああ、テレビの裏…」
「テレビの裏? そんなところに…」
「いや、箪笥と本棚の間…」
「箪笥と本棚の間? そんなところに…」
「いや、ベッドの下…」
「ベッドの下? そんなところに…」
「どこならいいんだよ?」と何故か彼が怒る。
「どこって…別にどこでもいいわよ」私は少し混乱しながら応じる。
「お菓子も欲しいな」と彼は場を取り繕うかのように告げる。「催促しているわけじゃないけどね」
私はまた一階へ降りる。戸棚を探してみる。これっていうのがない。冷蔵庫を見て…コーヒーゼリーはあるけど…紅茶には合わないかしら? どうしよう? 困るわね。あっ、バームクーヘンがある。仕舞い忘れたのかテーブルの上にバームクーヘンが居座っている。彼の口に合うかしら? っていうかバームクーヘンってどうやって出すの? 切ってから出したほうがいいのかしら。
私は普段全然手にしない包丁を使ってバームクーヘンを切り分ける。食べやすいぐらいの大きさを狙って。面倒なことだけど、やってみるとちょっと楽しいわね。うん、こういうの意外と悪くないわ。好きな人のためにっていうのが良いのよね。あっ、私もうあの人のこと好きになっちゃってるみたい。駄目駄目、あんまり意識したら、私までぎこちなくなっちゃう。あの人があんな調子なんだから、私はもっとしっかりしないと。
部屋へ戻ると彼は携帯で通話中らしい。「煙が出た?」と驚いている。私が戻ってきたのに気付いたようだけど、彼は引き続き何かを話す。あれ? カーテンが今度はまた閉じられている。っていうかちょっと待って。何だか焦げ臭くない? ……気のせいかしら? 一瞬匂った気がしたけど…今はもう匂わないわね。どこかに消えてしまったみたい。錯覚だったのかしら? そうね。だって火なんか使ってないでしょうし。え? まさかタバコ? でも吸殻とかそういう痕跡もない。大丈夫。思い過ごしよ。
そう言い聞かせながら私は床にペタンと座って彼を見上げる。やがて彼も電話を終えてクッションの上であぐらをかく。
「今の何の話?」バームクーヘンを差し出しながら、私は平静を装って尋ねてみる。
「少しだけ煙がどこからともなく出たらしいんだけど…でも出元がよくわからないらしい」
「どういうこと?」
「いや、そういう連絡があったんだ」
「そういう連絡?」ボヤ騒ぎでもあったのかしら? こんな湿っぽい季節に? と思いながら私は適当に返答する。「なんか大変そうね?」
「そんなに大変でもないようだった。はっきりと感じられないぐらいの煙だったみたいで。だからまだ決定的なことは何もわからない」
「そうなんだ」と私は相槌を打つ。何でだろう? 会話がグラグラしてる気がする。互いに言葉を積み重ねていくけど、それが少しづつズレてるから、不安定になっちゃうってことかしら…
「それで」と私はきちんと話をしようと思って少し慎重に彼に尋ねる。「どこの話なの?」
「どこって?」
「煙が出たっていうのは?」
「唐崎武雄の部屋だよ」彼はどこか試すような口ぶりでそう答える。
「唐崎武雄?」
「知らないの?」
「知らない…」っていうか聞いたことはあるような気がするけど…誰だったっけ?
「知らないのか…」と彼は意外そうな表情を見せる。まるで当然知っているだろうと思ってたみたいな…。どういうこと? 私と何か関わりがある人なの? 私が訝っていると彼が続ける。「向こうは君のことをよく知っているみたいだから」
向こうは私のことをよく知っている? でも私はその人をまるで知らない。一方的な関係? しかも私がその人を知らないことが意外そうに思われてる。…その人は、親しい間柄でないと知りえないようなことまで知っているってこと? え? まさかストーカーだとか? いや、まさかね。それはないでしょ。
「食べていいのかな?」と彼がバームクーヘンを指しながら不意に訊く。
「いいわよ、もちろん、どうぞ」
「いただきます」無邪気な笑顔で言ってから、彼はそれに手を付ける。一口モグモグとほうばって、「美味いな、これ」と呟いて。なんか…こうやって見るとのんびりした人ね。
「ところで」と彼が何か思いついたみたいに切り出す。「君はどういう男性が好き?」
「え?」ああ…本題に入ったのね? そうよね。それは大事よね。上手く答えないと…「そうねえ、やっぱりかっこいい人がいいわ。で、自分をしっかり持ってそうな人」
「なるほど」と西面君が頷く。そしてどこかあらぬ方向へ語りかけるようにいう。「これは諦めたほうがよさそうだ」
「え? なんで?」ちょっと諦めないでよ!「西面君もかっこいいよ。それに自分をしっかり持ってそうだし。なんか…深みがあるし、すごくいいと思う」
西面君は戸惑った表情でいう。
「ありがとう。なるほど…君は性格も悪くなさそうだ。……あ、これ、ごちそうさま」
「ああ、早いわね」と私はバームクーヘンの皿を乗せたお盆を脇へずらす。なんとなく…私はまた何かを催促されるような気がして、自分から彼に確認する。「他に欲しいものはない?」
「いや、いいよ。いろいろ試したけど、もう他に手が思いつかないし」彼は独り言のように話す。「あと、試すとしたら、あいつの詩の最後の一行だな」
「何を言っているの?」
「君の嫌なところを見たいな。目を背けたくなるような姿を」
「は?」この人どんだけミステリアスなの? とさすがに不安に駆られたところで彼は私を安心させようとしたのか取り繕うように続ける。
「俺は君のことをまだよく知らないからさ、君のことをもっとよく知りたいんだ。でも良いところは見てればだいたいわかる。だから嫌なところを見たいんだ。君のことを深く知るためにはそのほうがいい」
はあ…趣旨はわかったけど…。私を試しているのかしら? そうよ、やっぱりこの人だってちょっとは不安なのよ。私がややこしい女だったりしたら困るわけよ。だから確かめておきたいってことよ。私の嫌なところを。だから……なんとか上手い具合にしないと。ちゃんと嫌なところを見せないと、また会話がグラグラしちゃいそうだけど…でもそれで嫌われちゃったらもったいないし…ちょうど良い嫌なところってないかしら? 何よ、「ちょうど良い嫌なところ」って?
「例えばなんだけど…」名案が何も思いつかない私は、自分の嫌だなって思えるところをそのまま口に出してしまう。「友達とかさ、誰かが何かで成功したり活躍したりしたときにさ、ちゃんと称えられないの。なんか、ひがんじゃって、その子のこと悪くいっちゃうの。せっかくその子は頑張って成果をだしたっていうのに…私はその努力すらも否定するようなことを…」
「例えば?」
「例えば『そんなこと成功して何になるの? 私はそうはなりたくないわ~』みたいなことかしら…」
西面君はじっと深い目で私を見ている。なんか私余計なこといっちゃったかしら? そう思って私は言葉を重ねる。
「自分でもそういうところ嫌なの。でもそうなっちゃうの。そういうことを言わないと私がもたないの」私は何故か泣きそうになっている。どうしちゃったのかしら?
「駄目だ、それじゃ」と西面君がいう。「そんな健気な姿見せたら余計に惚れちまうよ」
あっ、告白だ! 今の科白は完全に告白よね?
「こんな私でもいい?」って私は上目遣いで彼に尋ねる。
「世の中にはね、嫉妬で他人を深く傷つけたり、陥れたりしながら平気な顔して生きている人間もいっぱいいるんだ。そういう奴らに比べれば、君は自覚や反省がある分だけマシだよ。断然ね」
「ありがとう…」
「君はきっと…世界一マシだ」
「ありがとう…?」喜んでいいのよね? 私が不安な顔を見せると彼は優しい目で微笑む。
「……君は本当にかわいいね」と彼は私を言葉で撫でる。「もういいや、いったんカーテンのことは忘れよう」
彼は私に寄り添って、私の髪をそっとその手で撫でてくれた。ここに来て彼の気持ちが私にまっすぐ向かってきているのを感じる。もう余計な駆け引きは要らない。言葉も要らない。彼の目線がそう語っている。そして彼は私にキスをする。私も抵抗しない。もうこれでいい。もう何も考えられない。なんだかんだと思考を巡らしているようだけど、これはルーレットの玉みたいに慣性でカラカラ回っているだけ。私の頭の中でカラカラカラカラ…。やがてその玉は赤い枠か、黒い枠か、どこかで止まるだろうけど、それすら私には決められない。傍から見ればそれは私の決断のように見えるのだろうけど、それはとっくに私の手を離れたものだ。
これで明日からは由美子や千春と対等に話せる。もう先延ばしなんかしたくない。っていうか今の私にとってはそんなことすらどうでもいい。
そうして私は彼に抱かれる。
「大丈夫?」終わってから彼が私に問い掛ける。「痛くなかった?」
「痛かった…」何故か私は正直に答える。「でも気持ち良かった」
「『最初は痛くて段々気持ち良くなる』ってよくいうけど、そういうこと?」
「……ちょっと違う気がする」
「違う?」
「厳密にいうと、痛い所と、気持ち良い所は近いけど別の箇所なのよ。でもなんかしびれて麻痺しているみたいでわけわかんなくなっちゃってて…」私は今恥ずかしさも麻痺しているようで、こんなことを平気で語っちゃってる。
「痛い所は今も痛い。気持ち良い所は最初から気持ち良かった……そういうことかな?」
「そうかもしれない……」でもやっぱりそんなにはっきりはしてない。
「またやりたいと思う?」
「うん…」私はどうしてだか彼に気持ちを伝えたくて、言葉を続ける。「だって痛みもあって、こういう感じなら…痛みがなければ、もっと…」
「だろうね」
「あのさ…」少しだけ不安な私は、彼に縋るように尋ねる。「付き合ってくれるんだよね?」
「もちろん」彼は即答してくれた。
恥ずかしくなったのか彼は私から目を逸らす。その時何かに気付いたのか急にその目は鋭い目に変わる。思わず私も彼の視線の先を追う。そこでは…大柄な全裸の男が真っ赤な顔でこっちを見ている。私は自分の耳をもつんざくような悲鳴を上げる。
「キャーーー」ーーー!!!
西面君が呟く。
「唐崎武雄…」
つづく
執筆者紹介
![山城窓[L] 山城窓[L]](http://nyankorogari.net/wp-content/uploads/2018/01/やましろさん-300x246.jpg)
山城窓
1978年、大阪出身。男性。
第86回文学界新人賞最終候補
第41回文藝賞最終候補
第2回ダ・ヴィンチ文学賞最終候補
メフィスト賞の誌上座談会(メフィスト2009.VOL3)で応募作品が取り上げられる。
R-1ぐらんぷり2010 2回戦進出
小説作品に、『鏡痛の友人』、『変性の”ハバエさん”』などがあります。
↓「いいね!」お願いしますm(_ _)m