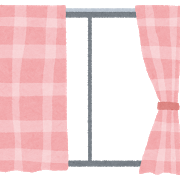七夕の風にひるがえるカーテン
ー⑤ー
山城窓
牧田圭介の悲しみ
三島江ゆかりの家のドアが開く。西面君が出てくる。三島江と何か言葉を交わしている。何故か西面君は三島江にキスをする。二人はまるで夫婦みたいに見える。僕は自分の頭を撫でる。唐崎に吹っ飛ばされて倒れたときに後頭部を打ったのだが…大丈夫。それほど強くは打っていない。大丈夫…だと思う。
別れが済んだのか、西面君は自分の家から出るみたいな当たり前の顔をして門から出てくる。
「唐崎は?」と西面君が僕に尋ねる。
「帰ったよ」
「全裸で?」
「いや…服は着たよ。ちゃんと渡した…っていうか僕を吹っ飛ばして、自転車籠から零れた紙袋から、勝手に服を見つけて着てた。それから…そこらへんで何かして……帰った」
「そこらへんで何か?」
「そう、そこらへん」と僕は西面君の自転車の辺りを指差す。
見ると西面君の自転車の後輪は明らかに空気が抜けている。
「パンク?」と僕が訊いてみる。西面君が自転車のタイヤを確かめながら答える。
「いや、たぶん空気を抜かれただけだな。バルブキャップがなくなってるし…バルブも緩められているよ。ま、このぐらいで済んでよかった」
「何がどうなってるの? 唐崎すっごい顔してたけど?」
「とりあえず君の家へ行こうか」
「どうして?」
「空気入れを借してもらう」
「三島江に借りれないのかな?」
「そろそろ親が帰ってくるかもしれないってさ。君の家近いんだろ? 行こうよ。歩きながら話そう」
「いいけど…」
そうして僕らは歩きながら話す。並んで自転車を押しながら。
「何にしても」と西面君が切り出す。「唐崎は留年を免れたみたいだな。ま、あいつが明日登校する気になるかどうかはわからないけどね」
「いや、だから唐崎に何があったの?」と僕は再び訊く。
「君のいったことが正しかったみたいだ。唐崎はカーテンになってた」
「なってたっていうのはどういうこと?」
「カーテンと一体化してたようだね。分子レベルで結合してたのか…。あるいは肉体に宿る筈の魂が裏返って、逆に肉体が魂に宿って、その魂が肉体もろともカーテンに含まれてたのか…そりゃ仕組みはわからないけど」
「そうなんだ…」僕はただそう返す。なんせ…よくわからない。
「で、俺はゆかりを抱いたんだ。そしたら、唐崎がカーテンの前に全裸で現れた」
「どういうこと?」
「唐崎は見たくなかったんだろうな。ゆかりが別の男に抱かれて喜んでいる姿を。ほら、彼の書いた詩にあっただろう?『君の見たくない姿を見るときまで カーテンになっていたい』とかさ。それで…見たくない姿を見たから元に戻ったってことじゃないか?」
「ああ…書いてたね、なるほど」
「それでさ、俺は唐崎と話をつけないといけないと思ったんだけど、まあ話にならなくて…最後は彼は全裸のまま部屋を飛び出してった。後は俺はゆかりに上手く話して誤魔化した…そんなところだな」
「誤魔化せたの?」
「どうにかなったみたいだ。『どういう手段を用いたのかはわからないけど、俺たちが夢中になっている間に、唐崎は窓から君の部屋に忍び込んだようだ。でも俺がちゃんとこらしめておいたから、もう大丈夫だ』ってなことを言ったら、『ありがとう、助けてくれて』って言ってたから」
「そんなことで…どうして誤魔化せるんだ?」僕は首を傾げる。
「どうしてって?」
「だって…その場合一番怪しいのは君だろう? 君が三島江の隙を付いて唐崎を招き入れてたっていう可能性が第一に考えられる筈じゃないか?」
「だって俺はそんなことしてないぜ?」
「そりゃそうだけど…」
「今の彼女はね、俺のいうことを驚くほど信じるよ」
「そうなの?」
「そういうものなんだよ。自分が選んだ男がくだらない男だとしたら、女の脳が困るんだ。だから脳が必死に言い聞かせてるんだ。西面真人には嘘や誤魔化しはないって。この人は信用できる人だって」
「へえー」僕はただ思いを口に出す。「なんか…わけわかんないや」
「そりゃそうだ」西面君が肯定する。「たぶん誰もわけわかってないよ。俺だってそうだし。それにしても…」
「何?」
「君はどうしてさっきから泣いてるんだ?」
……涙が頬を伝っているのを感じる。僕は泣いている。僕が言葉を返せないでいると、西面君が続ける。
「ま、そんな気はしてたけどね。最初から。君は唐崎を助けたいというよりは、自分の好きな女の体を唐崎に見られているということが耐えられないようだった。それで藁にも縋るような思いで俺に助けを求めたんじゃないか?」
「そうかな…」僕は彼から目を逸らす。見透かされることが怖くて。でも…まるで彼はすべてを見透かしているようだ。
「だって、そうでもないと…君は自ら動いてどうにかしようとなんかしないだろう。君にもとくに唐崎を助ける義理なんかないだろうし。カーテンになってるかもしれないと思ったって、それはきわめて可能性の低い話だったはずだ。でも君は…その仮定を想像して、それを強く恐れた。想像でも君はそれに耐えられなかったんだ」
僕は背中を探るように触る。頭を打ったことばかり気にしてたけど、背中もじんじんと痺れている。そこは大した傷ではないと思ってたけど…皮をすりむいているようだ。手が触れた瞬間に激痛が走って…僕は思わず顔をしかめる。
「好きなら好きっていえばよかったんだ」彼の言葉が僕の胸倉をつかむ。背中でシャツが傷に触れ、僕は身をよじって痛みに耐える。「どうして言わなかった? それとも自分でも気づいてなかった?」
「わからないよ」僕は痛みを堪えながら話す。「でも…そうかもしれない。ていうか…昔は好きだったんだ。でも僕は彼女の眼中に入っていないことに気付いてからは諦めて…」
「言い聞かせてたんだろうな。そうやって忘れようとしてたんだ。傷つかないように。でもやっぱり…無理があったんだろうな」
「君は…ヤな奴だな?」
「どうして?」
「人が…傷ついているってのに…」
「君までそんなこと言うのか?」呆れながら彼はいう。「君のはただの失恋だろ? しかもそういうレールを作ったのは君自身じゃないか? 俺はそのレールを素直に走っただけだぜ? 俺がゆかりに興味を持っていることにして…そうしてゆかりをその気にさせて。二人の距離を縮めていったのはそもそも君だろ?」
「わかってるよ、そんなことは」僕は言い返す。言い返さずにいられずに。「でも…だって、そんな簡単に…結ばれるとは思わないじゃないか?」
「今まで黙ってたけど…」彼は深刻な面持ちで告げる。「俺は男前なんだ」
「わざわざ自分から言い出すようなことでもないものね、それは」
「そうなのか?」
「そうだよ。そんなことより…僕が三島江のことを好きだって気付いてて…三島江を抱くなんて…酷いよ」
「抱かないわけにはいかなかったんだ」
「そんなことはないだろう?」
「それがあるんだよ。あそこまでその気にさせておいて、こっちが全然その気がないってことになったら…彼女は恥をかかされた、弄ばれたと思って怒り狂う。そういうときの女の怒りといったら、街をまるごと食い破るほどのエネルギーを持つ。俺の命に関わる。抱くしかないよ、そりゃ」
「大袈裟だよ…」
「いや、大袈裟じゃない。君も今日映画で見ただろ? サトカはタイジに弄ばれたと思い込んで、その怒りでただ近くにいたブ男の麦下に抱かれたんだぜ。仕返しのために。いわばタイジの心をへし折るために」
「あれは映画じゃないか?」
「映画だけど、事実を元にした映画だよ」
「そうなの? 詳しいね?」
「そりゃね。だってあの映画の脚本を書いてるのは玉川四郎だぜ?」
「知らないな」
「俺の本当の父親だよ」
「そうなの?」
「そうだよ」
「あの…芸人であり劇団員でもあるっていう?」
「芸人であり劇団員でもあり脚本も書いてるんだよ」
「そうなのか。だったら…言えばいいじゃないか? 映画を見るときにさ」
「これはわざわざ自分から言い出すようなことなのか?」
「だって…言うだろう? みんなでその映画見てるんだし…言うだろう?」ふと思いだして僕は問い掛ける。「それで君あの映画を選んだのか?」
「そうだよ」
「正直なんでこれなんだろうとは思ってたんだ。だから…言ってくれればよかったのに」
「まだなのか?」
「何が?」
「君の家だよ」
「ああ、そこだよ。白い家。茶色い屋根の…」僕は指差しながら彼に伝える。
「軒先に七夕飾りが出してある家か?」彼の視線は僕の示す方向と少しずれている。
「その手前だよ」
「ああ、なるほど」と西面君は頷く。ベカベカと空気が抜け切った自転車を押して、該当の建物の前で止まる。表札を確認する。「ここか?」
「そうだよ」と答えてから僕は自分の自転車を家と塀の間のスペースに押し込むように入れて、そこに停める。それからガレージの脇に掛けてある空気入れを手に取る。
「はい」といって僕はそれを西面君に渡す。
「綺麗な家じゃないか」と彼は僕の家を見上げたまま受け取る。それから自転車の後輪のバルブを探す。
「綺麗に見えるけど…中はそうでもないよ。散らかってたり、汚れてたり」
「どこの家もそういうものかもしれないな」彼は空気入れに体重を乗せるようにして空気を押し込む。タイヤが少しづつ生き返っていく。
「君の家は中も綺麗に片付いてたじゃないか?」
「さっき言っただろ? そこに住んでいる家族は…なかなかおぞましいよ。だって…わかるだろ? サトカと麦下が暮らしてるんだぜ? しかもそこにいる子供は麦下の子供ではなく玉川四郎の息子…つまり俺なんだぜ?」
「どういうこと?」
「帰らなくていいのか?」
「大丈夫。遅くなるっていってあるから。話してくれよ」僕は西面君の汚点を見たくなっている。それを引き摺り出せる気がして、僕はそうせがむ。
「話すといってもね、もうすでにおおまかな話を君は見てるんだよ。あの映画がつまり玉川四郎の実体験だ。役名でいうなら玉川四郎がつまりタイジだ」
僕は口を開けて、後頭部を撫でる。血は出てないようだけど、コブになってるな、と気付く。ゆっくりと頭を整理する。玉川四郎=タイジ。西面君のお母さん=サトカ。その旦那が麦下…。西面君は…タイジとサトカの子供。
「つまりだな」僕が混乱しているのを見越したのか西面君が語る。「俺の本当の母親は……ややこしいからこれも役名でいうけど、サトカはタイジを愛してたんだ。面と向かっては話ができなくなるほどに。しかも二人が出会った当時はサトカに彼氏がいた。ま、一人身になるのが嫌だからなんとなく付き合っているっていう恋人だったようだけどね。でもタイジは彼氏のいる女に近づいてはいけないと思ってた。根が真面目なんだ、あの男は。でもある日その彼氏のことで相談を持ち掛けられたから、『別れればいいじゃん』と言ってみたんだ。別れたならタイジはちゃんと責任を取るつもりだった。サトカは当時二十九歳で他人に独身であることをからかわれたりもしていて結婚を焦ってたからね。それでサトカもそもそもタイジのことが好きだったから、当時の彼氏と別れたんだ。だからね、『彼氏と別れちゃった』っていうことをサトカがタイジに伝えさえすれば、後は、タイジが『じゃあ、俺と付き合ってくれ』ってなって…まあ、そのうちに結婚してっていう、そんなただの幸せな話になる可能性もあったんだ。っていうかそうなるべきだったんだ。……返す」
西面君が不意に空気入れを僕に渡す。自転車のタイヤは完全に復活しているようだ。僕は空気入れを適当に片しながら尋ねる。
「でも、実際はそうならなかった?」
「そう。まず麦下だ。麦下は知ってたんだよ。タイジがサトカに彼氏と別れるようにいったことも、サトカがそれを聞いて喜んでいたことも。麦下もサトカのことが好きだったから嫉妬して、彼はタイジに嫌がらせをするようになった。タイジが注意しても麦下は反省せず嫌がらせを続けたから、タイジは麦下との縁を切った。はっきりと『関わりたくない』と伝えてね。で、麦下はいつも…休憩中も帰りもサトカと一緒にいたから、タイジはサトカに近づけなくなった。麦下がそういう事態をサトカに伝えていれば、サトカはどうにかしようとしただろう。でも麦下はそれを恐れた。伝えればサトカも自分と距離を置くと思ったんだろうね。だから誤魔化した。どうしてタイジがサトカに会いに来なくなったのか、それを訊かれても『さあどうしたんだろ?』ってはぐらかしてしまった。さらには『タイジはフワコのことをよく褒めてたよ』とかね、余計なことをいうわけだ。タイジがフワコを褒めてたのは事実でも、タイジの気持ちはフワコには向いてなかったのに。でも…サトカはただ不安になった」
星が見えないな、と僕は夜空を見上げて思った。分厚い雲が空を覆っている。そういえば、ここ数年天の川を見ていないな、と気付く。誰かと誰かを隔てているのが何なのかも、わからなくなってしまう……そういうこともある。西面君が続ける。
「そこにフワコが追い討ちを掛けた。タイジとフワコは同期でね。タイジは仕方なくサトカや麦下のいないほうの休憩室に行ってたんだけど、そこにはいつもフワコがいた。で、そこで大した意味もなく一緒に昼食を食べたりして、大した意味もない会話をしてたんだ。でもフワコはそこに厄介な意味を持たした。『あ、この人私のこと気に入っているんだ』ってね。もともとタイジってのはモテる男なんだよ。なんといっても俺の本当の父親だからね。それはそれはモテるんだ」
「いいよ、その話は」イラっときたせいか後頭部がズキっと痛んだ。
「まあ、それで…なんだっけ? そうそう、フワコはサトカと偶然会って話すんだ。最近タイジを見かけないってことをね。つまり元々休憩室でしか会う機会がなかったけど、その休憩室に顔を見せなくなったわけだから。それでフワコにそのことを訊いてみたら、フワコは言ってしまうんだ。『いつも私のところに来ているわよ』ってね。それを聞いてサトカは語る。タイジから彼氏と別れるようにいわれたことについて。もともとサトカは負けず嫌いだったり見栄っ張りだったりするからね。サトカの主張は『タイジはあくまでも私のことを想ってるんだからね』ってことだな。で、フワコは反論する。『タイジは冗談で別れればいいじゃんって言っただけなのに、それを真に受けてあなたが本当に彼氏と別れたから、タイジは引いちゃったのよ』ってね。で、サトカはそこから生じるイメージに、もう耐えられなかった。頭に来てちゃんとタイジに確かめもせずに復讐に転じてしまった。その復讐が麦下と付き合うことだった。なんせ、サトカは麦下が卑怯な真似をしているなんて夢にも想ってなかったからね。麦下はいつも近くにいたし、ちょうどよかったんだ。……聞いてるのか?」
「え? 聞いてるよ」
「別のことを考えている顔に見えた」
「思い出してたんだよ。映画の内容を」西面君の話に映画のイメージが重なって…しかも頭が痛んで…僕はどこか別の世界にでも流されてしまいそうな感覚に陥っていた。
「まあ、聞いているならいいや」と西面君は続ける。「そんなことで既にサトカはレールを外れてるんだけど…サトカ自身はそんなこと気がつかなかった。自分の母親のことをこういうとなんだけど…思慮深いとはいえない人間なんだ。自分の行為がどういう結果に結びつくかとか考えられない。オセロでもやったならそのとき一番多く石をひっくり返せる所に置いてしまうような。そして次第に置くところがなくなっていって追い詰められて、置きたくないところに置くしかなくなってしまうような、そんな人だ。で、やがてタイジは気付く。サトカとすれちがったときに、明らかに敵意を見せていることに。不審に想っていたら、これも偶然に聞いてしまうんだ。サトカと麦下が付き合っているって。しかもまもなく麦下はプロポーズする。なんせ麦下にも焦りがあったんだ。バレたらどうしようっていう気持ちからくる焦りだね。つまりバレる前に引き返せないところまで行ってしまおうって腹だな。それでサトカは完全に分別も見境もなくしてたからね、『もういいや、この人で』って感じで結婚を受け入れてしまう。それまでにもちろん何度かタイジはサトカと話をしようとはしてたけどね、サトカはタイジのすべての言葉を跳ね返した。サトカはもう何も考えられない状態だったんだ。言葉が頭に入れば考えることになるからね、本能がそれを避けて、言葉を払いのけるようになってた。それでタイジはある時何にも考えず、考えさせず、黙ってサトカに寄り添って抱きしめた。サトカも本能で受け入れた。もともと二人は愛し合ってたわけだからね。だからそのままタイジがサトカを奪い去ってしまえば、それはそれでハッピーエンドもありえたわけだよ。あまり綺麗ではないけど、納まるべきところに納まるということでね。でもタイジが気付いたんだ。その手で抱いた女はもう自分が愛した女ではないってね。そこにかつて愛した女の残像はあったが、よく見るとただの汚れた女がいただけだったって。なんせ麦下に抱かれた女だからね、気持ちはわからなくもない。それでタイジはサトカを奪いもせず、放っておく。サトカはやはり何も考えられず、そのまま麦下と結婚する。でもお腹には子供ができていた。タイジとのたった一度の性交でできた子供だけど、つまりそれが俺だ」
「なんだかよくわからないけど…」僕は感想を伝える。「無茶苦茶な話だね」
「まったくだ。無茶苦茶な話だ。でも『こんな馬鹿な話があるか?』って思うことでも現実に起こったりするんだ」
「でも…」
「何だよ?」
「どうして君はその話を知っているんだ?」
「聞いたんだよ。タイジから。つまり玉川四郎から」
「会ったの?」
「向こうが突然会いに来た。まだ寒かったから…四カ月ほど前だな。人伝に聞いたらしい。『サトカの子供が全然父親に似ていない。かといってサトカにもそれほど似てない。じゃ、誰に似てるかっていうとあんたによく似てる』って言われたそうだ。そもそも玉川四郎もサトカが自分の子供を身ごもっている可能性を感じていたんだ。だからあんな脚本を書いたわけだからね。それでもしかしたらと思って、わざわざ調べて俺に会いに来た。で、今の話を俺に聞かせた。俺の本当の父親だと名乗った上でね」
「それだとさ」僕は念のために尋ねる。「本当の父親かどうかわからないんじゃないか?」
「それからDNA鑑定をしたんだ。唾液を取ってね。それでわかるらしい。で、一カ月後にその結果が届いた。そうして確定的になった。俺が玉川四郎の息子だってことがね」
「なるほど」僕は言ってみる。「君はそれでずっとどこか様子がおかしかったのかな? 突拍子もないことをいったり、奇行を見せたり」
「いや、それは元々だ。俺は元々頭がおかしい。ただね、平気ではなかったな。何がなんだかわからないが…じゃあ玉川四郎が本当の父親なら、じゃあこの『父親』は誰なんだって思えてね。麦下っていったほうがわかりやすいか。戸籍上の父親であり、経済的にはずっと助けられていたわけだけど、血縁的には無関係なんだ。思えば愛されてもいなかったし。虐待というほどのことは何もされてないけど、物心ついたころからずっと恫喝と否定を繰り返されてきた気がするよ。俺が玉川四郎に似ていることについて、何かあったのかもしれないね。でも俺はどこかで父親というのは、そういうものかもしれないと思いながら…まあ耐えてたんだよ。
でも、だ。こうなってみると俺は何を耐えてたんだろうとも思えだした。血はつながっていないわけだし、しかもこの目の前の男は俺の母親の幸せを潰した男で、俺の本当の父親を陥れた男なんだ。だから俺はさっさと家を出ようと思った。玉川四郎も言ってたからね『もし家を出るなら金銭的な援助はする』ってさ。でも問題は母親なんだ。母親を見捨てるわけにはいかない。なんせ俺のことをすごく大事にしてくれた。俺を心の底から愛してくれた。母親にとっては俺が救いだったんだ。本当に愛した人の子供だからね。でも同時に母親は麦下についても良いように考えてた。そう言い聞かせていたんだ。この人と結婚して良かったんだ、これで幸せなんだって。だからたぶん彼女はまだ何も知らないんだろうね。だって自分の愛した人を陥れて、本当に好きな人と一緒になるっていう夢を潰した人間を、良いようになんか考えられるか? そんな人間と暮らすことが幸せだなんて思えるか? ま、彼女は相変わらず何も考えずに生きてきたんだろうけど。そういうわけで、俺は母親を守りたいんだけど、麦下と別れさせるためには、真実をすべて伝えないといけない。でもそれがひどく難しいわけだ。彼女はだって十何年も…俺が十六歳だから十七年ぐらいかな。ずっとこれで良いんだって自分に言い聞かせてたわけだからね。俺はその十七年もの歳月を否定することになる。…一度尋ねてはみたんだ。『俺の本当の父親は玉川四郎なの?』ってね。その一言だけで、彼女は頭を抱えてワナワナと震えて、その場に跪いたんだ。信じられないぐらい小心者なんだよ、彼女は。『誰から聞いたの?』って涙眼で訊くんだぜ? とてもじゃないが、すべてなんか語れなかったよ、その時は。伝えれば狂ってしまうんじゃないかって思えるような…あるいは死んでしまうんじゃないかって思えるような…そのぐらい彼女は打ちひしがれていたからね」
「じゃ、どうするの?」と僕は訊く。「そのまま暮らすの?」
「いや、そうはいかない。俺は真実は伝えられるべきだと思う」
「相手が狂ってしまうかもしれなくても?」
「そう。でももちろん、そうならないように気をつける」
「どういうこと?」
「感じてもらうんだよ。その真実を知ることには痛みが伴うだろうが、その先にそれ以上の快感があるっていうことをね。で、快感によって麻痺させて傷みを誤魔化す。そしてその痛みはやがて消えるものだっていうことも知ってもらう。そしてただただ快感を追いかけて、自分から真実を欲するようになってもらう」
「よく…わからないや」
「君にはまだ早い話だよ。俺もさっき気付いたことだ」
「さっき?」
「ゆかりが気付かせてくれた」
「三島江が?」
「まあ、いいよ。そこは君は聞かないほうがいい。君がまた凹むだけだ」
僕は首を傾げながら曖昧に相槌を打つ。ただ言われたとおり、それ以上聞かないようにする。
「それで」と僕は質問を改める。「お父さんのほうは……麦下のほうは大丈夫なの?」
「大丈夫ではないな。母親にどうにか真実を伝えて、離婚してもらうとして、麦下が納得するかっていうと納得なんかしない。はっきり言ってしまうなら俺がこいつを殺すべきかもしれないとも考えた。誰かがそれをしないといけないなら、未成年の俺が罪も軽い分適任かなってね。でもね、さっき思い直した」
「さっき?」
「そう、さっき。こいつは自分が何をやっているのかもわかってないんだろうな、ってね。気付いてしまったんだよ。後ろめたさもあることはあるんだろうけど、最終的にモーションを掛けてきたのはサトカのほうだからね。何がどうなってそうなったか、自分の行為がその後どうつながっていったかなんかわかっちゃいないんだ。だからあんなにしれ~と暮らしていられるんだ。そんな…自分が何をしたかわかっていない者に対しては…怒る気も失せたよ」
さっき三島江の家で何があったんだろう?と思ったが…西面君がそこを語らないから僕も聞かなかった。
「だから」西面君が続ける。「問題は山積みだ。状況が絶望的なことに変わりはない。でもね…俺は今日希望を持てた」
「希望?」
「そうだよ。だって唐崎はカーテンになってたんだぜ? 人はカーテンにならないっていうのが甘い幻想で、人はカーテンになることもあるっていうのが現実なんだ。世の中には絶対なんかないんだよ。絶望も例外じゃない。絶対の絶望が存在しないということは、そこには希望が残されているということだ」
西面君は力強くそういう。僕は…いまいち釈然としない。希望が残されているなら、それはそもそも絶望じゃないんじゃないか。それに…唐崎は本当にカーテンになってたんだろうか、って疑念も僕の中から消えてない。だってわからないじゃないか? 唐崎は本当に窓から忍び込んだのかもしれないじゃないか? 暑さと欲情のあまりおかしくなって全裸で…
「何なら試してみようか?」僕が腑に落ちていないことに気付いたのか、西面君が問い掛ける。
「試す? 何を?」
「そうだな…」彼は旅行の計画でも練るような顔でどこか楽しそうに語る。「俺が他の女に手を出して、ゆかりと君を結びつけるってのはどうだ?」
「は?」僕は彼の提案をまったく飲み込めない。
「俺が別の女に手を出す。で、ゆかりとはただの遊びだったってことにする。そうすると、ゆかりは弄ばれたと怒り狂って、復讐のために見境なく手ごろな男と付き合う可能性がある。苦しみから出来るだけ早く脱しようとしてね。だから君はその時出来るだけゆかりの近くにいればいい。それだけでゆかりは君を選ぶ可能性が高い。…ビリヤードみたいなもんだな。角度と距離感を間違えなければ、狙ったところにポケットできる。本来なら君がゆかりと付き合うのはまず不可能だ、絶望的にね。でもこの方法を使えばその不可能を可能にすることだってできるかもしれない。さ、どうする?」
「帰ってくれ」僕の声は震えている。ただ…虫唾が走った。
「よし、それでいい」彼は満足そうな顔で頷く。まるで僕の反応も計算づくだったみたいに。「本当に今日は親の仇を討ったような気分だよ。じゃ、君はこれからも…なるなよ。麦下やらカーテンやらに」
彼は不意に自転車にまたがり、そのまま漕ぎ出す。その自転車の後輪は力を漲らせているようで、軽やかにその車両を前へ運ぶ。僕は…呆然とそれを見送る。
仕方なく家に帰る。親はもう寝てるのか、妙に静かだ。僕も音を立てずに階段を上がり自分の部屋へ入る。電気を点ける。夜の暗さを確かめるように、僕は窓際に立つ。外を見ると、隣家の軒先にはまだ七夕飾りが出されたままになっている。夜風にくすぐられて、短冊たちが身を捩っている。そこには叶えられるべき願いと、叶えられてはいけない願いがあって…でも神様からしたらそんなことは知ったことじゃないんだろうなあ、なんて思いながら、僕は部屋のカーテンを閉める。
〈了〉
執筆者紹介
![山城窓[L] 山城窓[L]](http://nyankorogari.net/wp-content/uploads/2018/01/やましろさん-300x246.jpg)
山城窓
1978年、大阪出身。男性。
第86回文学界新人賞最終候補
第41回文藝賞最終候補
第2回ダ・ヴィンチ文学賞最終候補
メフィスト賞の誌上座談会(メフィスト2009.VOL3)で応募作品が取り上げられる。
R-1ぐらんぷり2010 2回戦進出
小説作品に、『鏡痛の友人』、『変性の”ハバエさん”』などがあります。
↓「like」ボタンのクリックお願いしますm(_ _)m